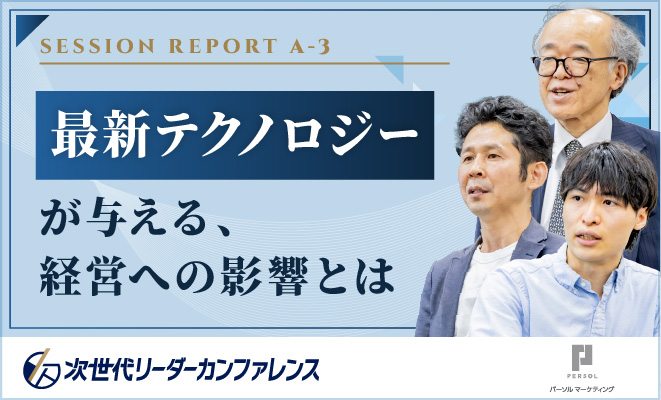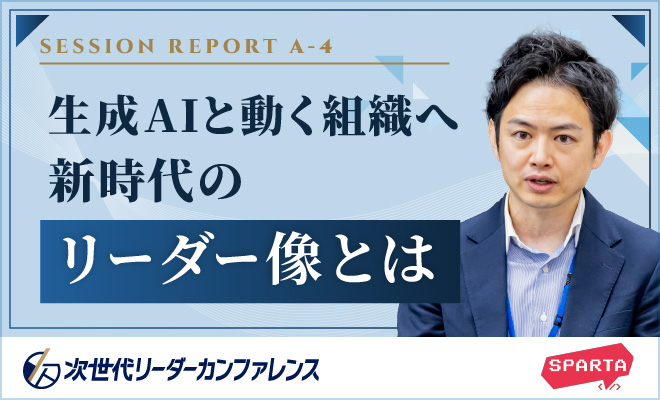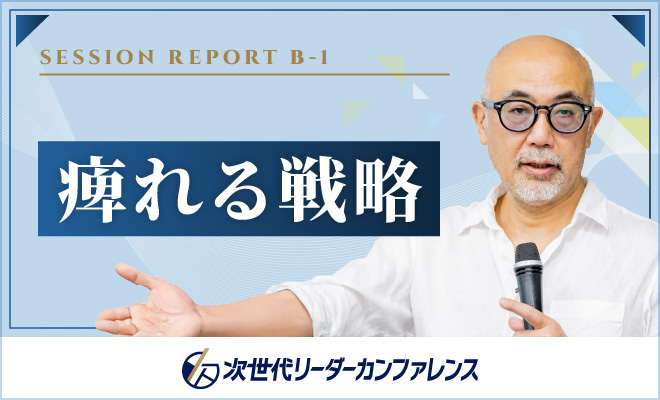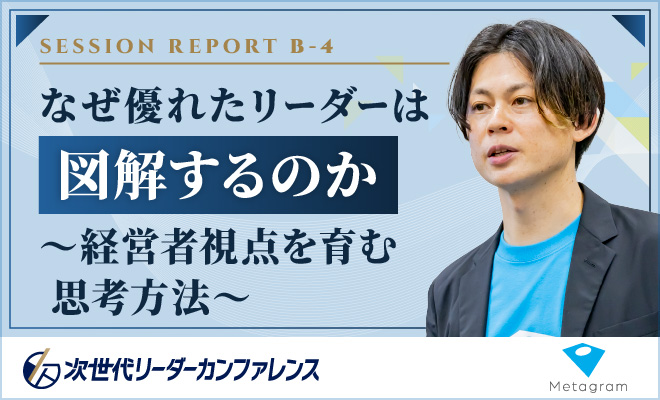目的ではない、手段としての「イノベーション」
米倉 誠一郎氏(一橋大学 名誉教授/デジタルハリウッド大学院 特命教授/県立広島大学院 経営管理研究科長/ ソーシャル・イノベーション・スクール 学長)
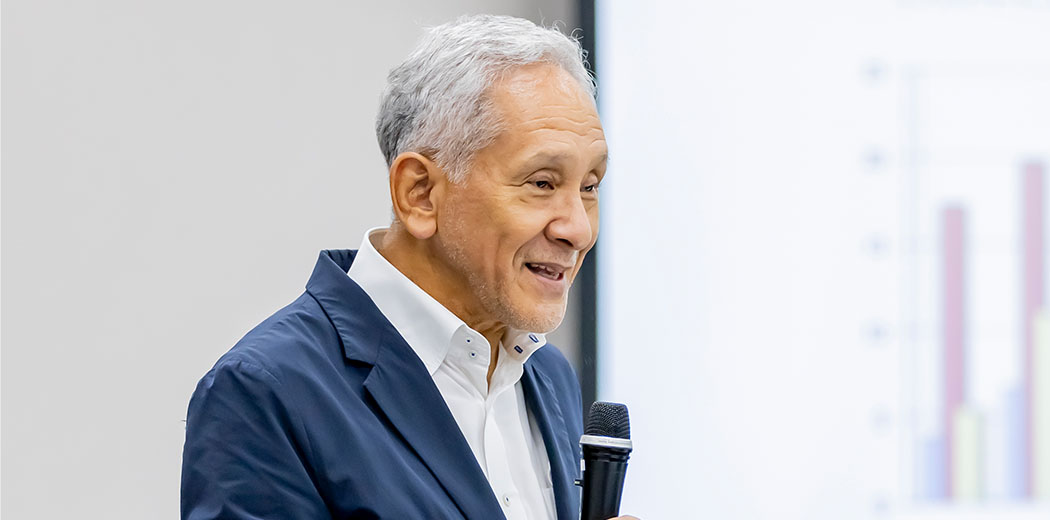
昨今、多くの企業がスローガンのように「イノベーション」を掲げているが、その言葉自体が目的化し、思考停止を招いてはいないだろうか。一橋大学名誉教授の米倉誠一郎氏は、イノベーションはあくまで「手段」であると強調する。本講演では、次世代のリーダーが真に取り組むべき課題として「教育」「環境(SDGs)」「生産性」の三つを挙げ、日本の歴史的成功体験の解説と厳しい現状の分析を交えながら、未来への処方箋を提示。危機的状況を直視し、世界に視野を広げ、日本の真の強みを活かすことで道は開けると、米倉氏から次世代リーダーへメッセージが送られた。

- 米倉 誠一郎氏
- 一橋大学 名誉教授/デジタルハリウッド大学院 特命教授/県立広島大学院 経営管理研究科長/ ソーシャル・イノベーション・スクール 学長
「イノベーション」という言葉の罠
――なぜ今、その使用を避けるのか
講演の冒頭で米倉誠一郎氏は、自身が1997年に国立大学初のイノベーション研究センターを設立して以来、28年間専門としてきた「イノベーション」という言葉を、最近はあえて封印していると語った。多くの企業で「イノベーション推進室」といった部署が設置されているが、「イノベーションを行っている」という会社で、本当のイノベーションが起きているのを見たことがないという。
「イノベーションという言葉は、それ自体が目的であるかのように扱われることで、本来問われるべき『何のために行うのか』という上位概念を見失わせる思考停止のワードになっています。本来、イノベーションとは、顧客に最高の価値を届け、高い生産性と利益率を実現し、世界でトップを目指すといった厳しい挑戦の結果として、第三者から『あれがイノベーションだった」と評価されるものです」
米倉氏は、次世代リーダーは「イノベーション」という便利な言葉に逃げるのではなく、自社が、そして日本が成し遂げるべき具体的な目標をまず設定すべきだと強く訴える。その上で、資本主義というシステムの本質に触れた。
社会主義が「富の分配」には長けていても「創造」はできないのに対し、資本主義はイノベーションを中核に据え、富を創造する力を持つ。中国が1979年に鄧小平のもと市場経済へ舵を切って以降、驚異的な発展を遂げたのがその証左である。
例えば「釘(くぎ)を1トン作れ」といった計画経済の命令では、消費者が本当に求める多様な釘は生まれない。競争と創意工夫こそが、価値創造の源泉なのだ。しかし、そのダイナミズムは必然的に格差を生む。その差を埋めるために必要なのは、大衆迎合的な政策ではなく、企業による「リスキリング」への本質的な投資であると米倉氏は強調した。
日本の奇跡的な復興を支えた「教育への投資」という原点
では、次世代リーダーが取り組むべき具体的な目標とは何か。米倉氏はその筆頭に「教育」を挙げる。その根拠として、日本の近代化と戦後復興の歴史をひもといた。
第二次世界大戦により、日本は焦土と化した。しかし、わずか30〜40年で目覚ましい発展を遂げた。世界の人が「奇跡」と呼んだその原動力は、決して奇跡ではなく、「投資の結果」であった。
明治初期、日本の義務教育就学率は30%未満だったが、わずか40年後の1910年(明治末期)には97%に達し、当時の教育大国アメリカに迫る水準となった。この教育への投資が花開いたのが、1950〜60年代の高度経済成長期である。均質で規律ある労働力が、奇跡と呼ばれる経済成長の原動力となったのだ。
さらに米倉氏は、1917年に渋沢栄一と高峰譲吉が「戦艦一隻分の予算で研究所を作るべきだ」と提唱し、理化学研究所(理研)を設立した事例を挙げる。「戦艦はそのうち錆びていくが、研究所は日々に新しい発明を生み、日本を繁栄に導く」。この先見の明が、湯川秀樹をはじめとするノーベル賞学者を輩出し、日本の科学技術の礎を築いた。アジア人初の非英語圏からのノーベル賞受賞という快挙は、敗戦に打ちひしがれた日本国民に「やればできる」という大きな希望を与えたのである。
しかし、現代の日本に目を転じると、その姿は大きく異なると米倉氏は警鐘を鳴らす。世界の大学ランキングで東京大学は30位台に甘んじ、特に女子学生比率の低さは深刻である。また、GDPに占める公的教育支出の割合はOECD平均を大きく下回り、教育への投資が著しく不足している。
「日本の国家予算は、収入の半分近くを借金に頼り、その支出の多くが社会保障費と過去の借金の利払いに充てられています。未来への投資である教育費に使えるのは、全体のわずか4.7%程度。これでは国力が衰えるのは当然です」
米倉氏は国の財政構造の歪みを厳しく批判。税収が上振れしても、未来への投資や借金返済ではなく、還元策ばかりが議論される政治の現状に、次世代リーダーは危機感を持つべきだと訴えた。

危機を好機に変える楽観主義
――世界の課題解決に日本の強みを活かす
教育と並び、米倉氏が次世代リーダーの挑戦すべき分野として挙げるのが「環境(SDGs)」である。ウィンストン・チャーチルの「悲観主義者はあらゆる好機の中に困難を見るが、楽観主義者はあらゆる困難の中に好機を見る」という言葉を引用し、日本は今こそ楽観主義に立つべきだと語った。チャーチルがこの言葉を語ったのは、ロンドンがナチスの空爆にさらされる絶望的な状況下であったという。「悲観は気分の問題だが、楽観は意志の問題だ」。困難な状況だからこそ、意志の力で未来を切り開くべきだというのだ。
歴史を振り返れば、日本は常に危機をバネにしてきた。アヘン戦争を目の当たりにした幕末の志士たちは、欧米列強に伍するため近代化を急ぎ、「デモクラシー」を「民主主義」と、「バンク」を「銀行」と訳すなど、海外の概念を一つひとつ取り入れ、わずか23年で基幹産業だった綿糸の輸出を輸入より多くすることに成功した。
しかし、日清・日露戦争の勝利で「日本は超大国だ」という慢心が生まれる。その成功体験への過信が、無謀な第二次世界大戦へと突き進む「失敗の本質」だった。国富の4分の1と310万人の命を失うという壊滅的な敗戦。ところが日本は、わずか15年後には「オリンピックをやりたい」と手を挙げた。1964年の東京オリンピックは、新幹線や高速道路といったインフラを整備し、日本が「経済で世界一になる」という新たな目標に向かって一丸となる象徴的な出来事となった。
そして1973年、オイルショックが日本を襲う。エネルギー価格が4倍に高騰する未曾有の危機に、日本企業は政府に助けを求めることなく、血のにじむような努力で世界一の省エネ技術と高品質な製品を生み出し、国際競争力を高めた。
「『資源がない、だから頑張ろう』。この危機意識が日本を強くしたのです。今、電気代を『下げろ』と言う声がありますが、それでは工夫が生まれなくなってしまう。2011年の計画停電のような経験を活かせば、もっと少ないエネルギーで快適な生活を送るイノベーションが生まれたはずです」
「もったいない」という精神や、世界が驚くほど清潔な都市環境など、日本にはSDGsに通じる文化が根付いている。この危機を乗り越えてきた日本の経験と技術こそ、世界の課題解決に貢献できると米倉氏は説いた。
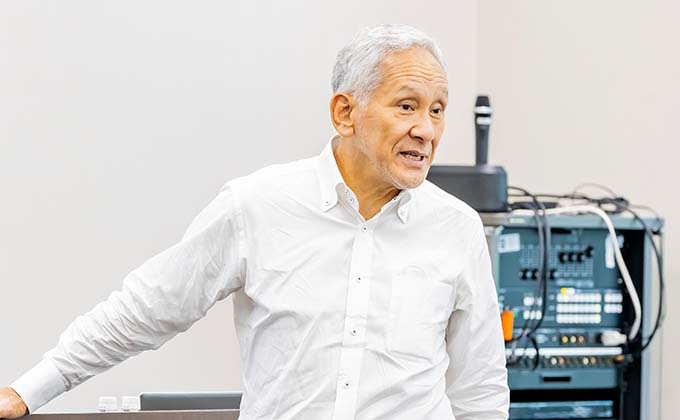
世界市場と日本の若者
――閉塞感を打ち破るグローバルな視点
少子高齢化が進む日本国内だけを見ていると、若者は「自分たちの稼ぎが高齢者の社会保障費に消えていく」という閉塞感にさいなまれがちだ。しかし、米倉氏は「視点を変えよ」と力説する。
「日本国内で考えたらマイノリティかもしれませんが、インドネシアの2億8000万人、インドの13億人の若者と組めば、マジョリティです。世界に行けば、若者がたくさんいるし、巨大なマーケットが広がっています」
特に米倉氏が注目するのが、2050年には25億人市場へと成長するアフリカ大陸だ。中国、アメリカ、ヨーロッパ主要国、そして日本がすっぽりと収まってしまうほどの広大な大陸が、爆発的な成長を遂げようとしている。しかし、彼らが先進国と同じライフスタイルを送れば、地球環境は持続不可能になる。そこに日本の出番があると米倉氏は言う。
「現地に行かなければ分からないニーズは無数に存在します。例えば、子供たちが水汲みの重労働から解放される『給水ローリー』や、現金収入が乏しい家庭でも手に入れられる仕組みをセットで提供する『ソーラーランプ』。こうした小さな、しかし生活を劇的に変えるイノベーションの種は世界中に転がっています。さらに、GEがインドで開発したポータブルな超音波診断装置は、もともと僻地の医療のために作られましたが、今では先進国での往診などでも需要が生まれています。リバースイノベーションです」
日本が培ってきた省エネルギー、水処理、公共交通、コンパクトな都市設計といった「パッケージ」は大きな価値を持つ。例えば、年間遅延時間がわずか17秒という日本の新幹線システムや、施工技術が未熟な地域でも水漏れの心配がないユニットバスは、そのまま輸出できる強力なソリューションだ。
日本の強みは技術だけではない。隈研吾氏や安藤忠雄氏に代表される建築や、漫画、アニメといったコンテンツ産業も世界で高く評価されている。これらのソフトパワーと、日本の優れたインフラ技術を組み合わせる「ニューコンビネーション(新結合)」こそ、シュンペーターが定義したイノベーションそのものであり、次世代リーダーは国内の縮小する市場を嘆くのではなく、世界に広がる機会を捉えに行くべきだと米倉氏は熱を込めて語った。
生産性低迷からの脱却
――次世代リーダーが目指すべき具体的な目標
最後に米倉氏が挙げた課題は「生産性」である。1998年からの約20年間で、中国の経済規模が14.38倍に成長したのに対し、日本はわずか1.23倍の成長に留まった。驚くべきは韓国で、日本よりも劣悪な資源環境にありながら4.26倍の成長を遂げている。その結果、OECD諸国の中で日本の労働生産性は30位、平均賃金も25位と低迷しているのが現実だ(2022年時点)。
生産性(1時間あたりの付加価値)を上げる方法はシンプルで、付加価値(アウトプット)を上げるか、労働時間(インプット)を減らすかの二択である。米倉氏は、特に付加価値向上の重要性を強調する。日本の自動車は高品質だが、フェラーリやポルシェのような圧倒的なブランド価値、すなわち高い付加価値を持つ製品を生み出せていない。日本にもユニクロのような成功例はあるが、世界で戦える高付加価値ブランドをさらに生み出す必要があると説く。
もう一つは労働時間の削減、すなわち創造性の発揮だ。「人がやらなくてもいいことを、いかに機械やデジタルに任せるか」。効率化を進め、人間はより創造的な仕事に集中することで、生産性は向上し、幸福度も高まるという研究結果もある。

米倉氏は、次世代リーダーに具体的な目標設定を促す。
「5年以内に、自社の生産性を世界トップレベルに引き上げる。平均賃金で少なくともイタリアや韓国を上回る。そうした具体的な目標を掲げたとき、初めてそれを達成するための手段として、どんなイノベーションが必要かというアイデアが生まれるのです」
教育に投資し、世界の環境課題をビジネスチャンスと捉え、自社の生産性を世界レベルに引き上げる。米倉氏が提示した三つの挑戦は、次世代のリーダーが日本の未来を切り開くための、明確かつ力強い道しるべとなるであろう。