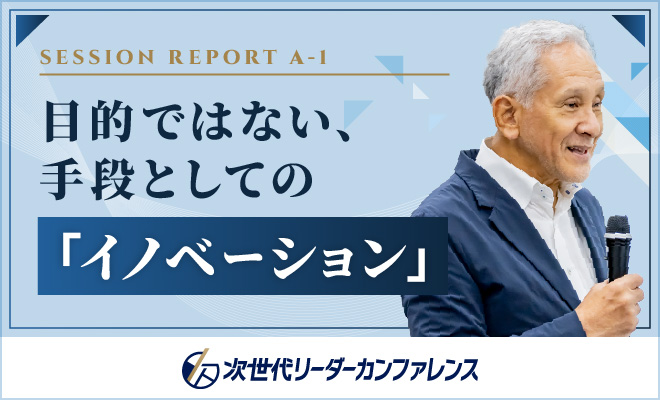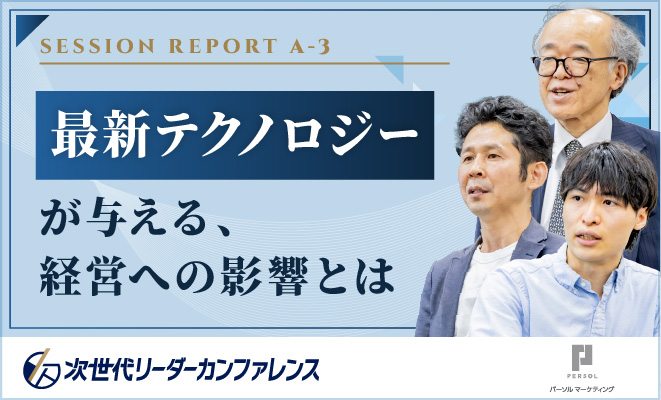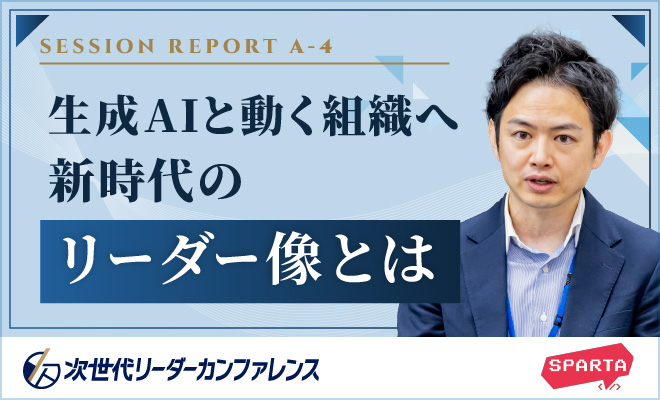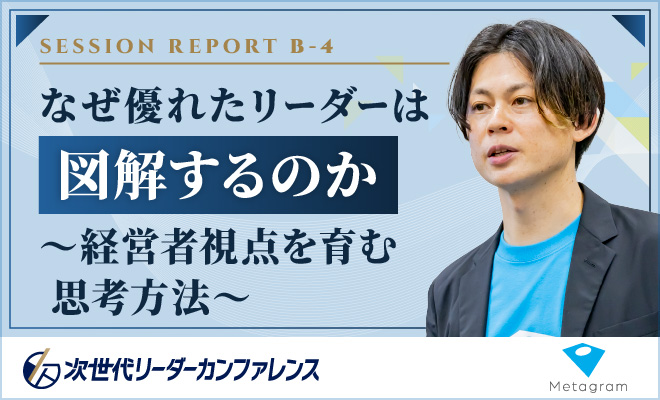痺れる戦略
楠木 建氏(一橋ビジネススクール 特任教授)

「痺(しび)れる戦略」とは何か。一橋大学ビジネススクール特任教授の楠木建氏は、戦略の本質は個別の打ち手の優劣にあるのではなく、一見非合理に見える要素さえも組み込んだ、強力な因果論理で結ばれた「ストーリー」にあるという。なぜマクドナルドはデリバリーで勝ち、トラスコ中山は業界の常識に反して成長するのか。数々の企業の事例を基に、優れた戦略が模倣を寄せ付けず、時には模倣しようとする競合を自滅に導く、そのダイナミックな論理を語った。

- 楠木 建氏
- 一橋ビジネススクール 特任教授
なぜ「長期利益」を他の重要指標よりも優先すべきなのか
現代の経営において、顧客満足、従業員エンゲージメント、社会貢献(ESG・SDGs)など、企業が追求すべき価値は多岐にわたる。楠木氏はこれら全ての根幹にあり、あらゆる企業活動の判断基準となるゴールはただ一つ、「長期的な利益の創出」であると断言する。なぜなら、利益は他の重要な価値を実現するための「元手」になるからだ。
「利益が出ていれば、他の大切なことを実現できます。あるいは、すでに実現されているから利益が出ているとも言えるでしょう。逆に利益が出なくなれば、それらを達成するのは困難です」
楠木氏は、顧客満足度を測る最も重要な指標も長期利益だと強調する。利益が出ていないのに顧客が満足しているとすれば、それは持続可能ではなく、ビジネスモデルのどこかに矛盾を抱えている可能性が高い。従業員の賃上げも、利益というパイがあって初めて実現できるのであり、経営者は分配方法の前に、まずパイそのものを大きくすることに注力すべきだという。
この考え方は、渋沢栄一が説いた「論語と算盤(そろばん)」の本質にも通じる。楠木氏は、道徳(論語)と利益追求(算盤)を対立するもの、あるいはバランスを取るべきものと捉えるのは誤解だと指摘する。
「渋沢栄一は、利益だけを追求しても結局は儲(もう)からないと言っているんです。なぜなら、道徳にかなった商売こそが、一番長期でがっつりと儲かるからです。真の顧客満足とは、顧客がその価値を認めて対価を払い続けることであり、その結果として企業に長期的な利益がもたらされる。つまり、経営者が儲けたいと願うなら、必然的に論語と算盤は両立します。これが、日本近代資本主義がたどり着いた知の結論です」
ESGも同様に、環境や社会、ガバナンスに問題のある企業は、顧客や優秀な人材から選ばれず、結果として儲からなくなる。ESGは利益と対立するものではなく、長期利益を追求する上で不可欠な要素なのだ。だからこそ経営者は、自社の事業で利益を出すことに集中すべきなのである。
企業の第一の社会的責任は、事業を通じて利益を上げ、経済を回していくことにある。その基本に立ち返ることこそが、次世代のリーダーに求められる姿勢だと楠木氏は語る。
戦略とは「なぜ儲かるのか」を語る因果論理のストーリーである
どうすれば企業は長期利益を生み出すことができるのか。その鍵は自著のタイトルでもある「ストーリーとしての競争戦略」にあると楠木氏は語る。多くの企業で語られる戦略が機能しない最大の理由は、それが「ストーリー」になっておらず、重要なキーワードを並べただけの箇条書きになっているからだ。
楠木氏は、打ち手の組み合わせだけで戦略を語ることを「二流経営者の特徴」と厳しく指摘する。
「挙げた打ち手の一つひとつは重要なことかもしれません。しかし、それらの打ち手がどうつながり、結果として『なぜ儲かるのか』という問いに答える論理がない。シナジーという言葉が安易に使われますが、現実の競争において、要素を組み合わせただけでは競争優位を築くことはできません」

真の戦略とは、個々の打ち手が「なぜ儲かるのか」という問いに答える原因と結果(因果)の論理で結ばれた「順列(パーミュテーション)」、すなわちストーリーでなければならない。
その好例として、楠木氏は日本マクドナルドのデリバリー戦略を挙げた。コロナ禍で需要が急増する中、同社は自社の「マックデリバリー」に加えて「Uber Eats」の活用を全面的に進めた。自社のデリバリー事業への投資を無駄にし、貴重な顧客データをUberに渡す非合理な判断のように思えるが、どのような戦略を描いていたのだろうか。
この戦略ストーリーの肝は、Uber Eatsの配達員の視点にある。彼らにとって最も重要なのは「配達頻度」。高いほど、収入は増える。マクドナルドは他の飲食店に比べて圧倒的に提供スピードが速い。主力商品のフライドポテトは揚げてから7分で提供できなければ廃棄するという厳格なルールがあるほどだ。
「Uber Eatsの配達員は、注文が来る前からマクドナルドの店の前で待機します。たくさんの注文が入ることが事前に分かっているからです。注文が入れば、すぐに受け取って配達先に向かう。お客さまにとっても温かいものが早く届く。だからリピートが増えたのです」
「提供スピードの速さ」が「配達員の待ち時間短縮」につながり、「配達頻度の向上」という価値を生む。結果として多くの配達員がマクドナルドに集まり、それが「顧客への迅速な配達」と「高い満足度」を実現し、さらなる注文を呼ぶ。
この好循環こそが、打ち手が因果でつながった儲かるストーリーである。単に「Uber Eatsを導入した」という事実だけを見ていては、この戦略の本質は見えない。重要なのは、打ち手がどのような因果のつながりの中に置かれているかである。
一見“非合理”な打ち手こそが、模倣困難な競争優位の源泉「クリティカルコア」となる
優れた戦略ストーリーには、その業界の常識家から見れば「なぜそんなことをするのか」と思われるような、非合理な打ち手が含まれている。楠木氏はこれを、戦略ストーリー全体の合理性を担保する「クリティカルコア」と呼ぶ。
その典型例が、工場で使われる工具や備品などの間接資材を扱う専門商社、トラスコ中山だ。卸売業の常識では、在庫をいかに効率よく回転させるか、すなわち「在庫回転率」の向上が収益性を高めるための鉄則である。しかし、トラスコ中山の戦略はこの常識に真っ向から反する。
「トラスコ中山の社長である中山哲也さんに話を聞いたとき、『私たちは在庫回転率を一切見ていません。そんなものを追求して、お客さまにとって良いことがあるのでしょうか』とおっしゃっていました」
同社が追求するのは「在庫ヒット率」、つまり顧客からの注文に対し、自社の在庫からすぐに出荷できる割合だ。90%を超える在庫ヒット率を実現するために、膨大な種類の在庫を抱え、巨大倉庫に投資し続けている。
これは在庫回転率を犠牲にする行為であり、短期的な効率を見れば極めて非合理だ。しかし、顧客が最も求めているのは「とにかく早く、確実に商品が届くこと」である。この本質を捉えれば、同社の戦略が絶大な顧客価値を生むことが分かる。
「在庫回転率を犠牲にして在庫ヒット率を極大化する」という打ち手こそが、トラスコ中山のクリティカルコアだ。競合他社は、「高い在庫回転率こそが正義」という業界の常識に縛られているため、まねしようとすら思わない。ここに「まねできない」のではなく「そもそもまねしようと思わない」という、強力な模倣困難性が生まれる。
「ストーリー全体を見ると儲かるようになっている。しかし、一つひとつやっていることをばらして見ると、業界に詳しい人ほど『バカじゃないの』と思うことをやっている。まさにトラスコ中山の戦略に痺れるわけです」
この論理は、格安航空会社(LCC)の原型を作ったサウスウエスト航空にも通じる。同社は航空業界の常識であった「ハブ&スポーク」システムを採用せず、あえて利便性の高いハブ空港を避けて地点間を結ぶ「ポイント・トゥ・ポイント」方式を採用した。業界の合理性から外れている一見すると愚かな打ち手が、他の打ち手とつながることで全く新しい論理を構築し、持続的な競争優位をもたらした。

アイリスオーヤマの強さの根幹にある「メーカーベンダー」というクリティカルコア
「なるほど家電」でおなじみのアイリスオーヤマ。その強さの根幹にも、巧みな戦略ストーリーとクリティカルコアが存在する。同社の開発コンセプトは「ユーザーイン」。これは、市場全体の平均的なニーズを見る「マーケットイン」とは異なり、特定の一人(n=1)の生活者の不満や困りごとを起点とするアプローチである。
「ユーザーイン」を可能にしているクリティカルコアは、アイリスオーヤマが「メーカーベンダー」であることだと楠木氏は分析する。
「ベンダーが一生懸命売ろうとすればするほど、メーカーはマーケットインに近づいていき、ユーザーの情報や洞察がゆがみます。しかし、アイリスはベンダーを自らやることで、ユーザーインを実現しているのです」
卸売を自社で行うと手間やコストがかかる。しかし非効率な仕組みが、生活者の真のニーズをダイレクトに吸い上げ、これまでにないヒット商品を生み出すことにつながる。このストーリーを中核に置くと、同社の他のユニークな打ち手の合理性も明らかになる。
例えば、製造業の常識では工場の稼働率は100%を目指すべきだが、アイリスオーヤマはあえて7割程度に抑えている。また、部品の内製化にもこだわっている。これらは一見、非効率で時代遅れに見える。しかし、「余力」があるからこそ、コロナ禍でのマスクの増産や災害時の需要急増など、緊急事態の場面で他社には不可能なスピードで対応し、飛躍的な成長を遂げることができた。
これらの打ち手は、単なる「逆張り」ではない。ユーザーインを起点とした自社のストーリーを貫くために、業界の常識とは異なる打ち手を合理的に選択している「裏張り」なのだと楠木氏は語った。
究極の競争優位とは「模倣させ、自滅させる」こと――仙台のコギャル仮説
優れた戦略ストーリーがもたらす競争優位は、単に模倣されにくいことだけにとどまらない。究極の戦略は「競争相手に模倣させることで、相手を自滅に導く」力を持つと楠木氏は語る。このメカニズムを、ユニークな「仙台のコギャル仮説」で説明した。
かつて流行したコギャルファッション。楠木氏が仙台で見た女子高生たちは、流行の発信源である渋谷のコギャルよりも、あらゆる要素が過激になっていたという。彼女たちは最先端のファッションを忠実に再現しているつもりでも、各要素を個別に取り入れて過剰に実行した結果、全体のバランスが崩れ、本来のコギャルファッションとはかけ離れたものになっていた。
この「模倣の過剰」は、ビジネスの世界でも起こる。90年代、アメリカの自動車会社であるフォードは、トヨタ生産方式(TPS:Toyota Production System)※を徹底的に模倣しようとした。しかし、「ジャスト・イン・タイム」という構成要素だけを過剰に追求した結果、巨大な設備を導入してしまい、「現場で問題を発見し改善する」というTPS本来の目的を見失って失敗した。
「ストーリー全体のつながりが分かっていない状態で、目に見えるベストプラクティスだけを模倣しようとすると、ついやりすぎてしまうのです。」
優れた戦略ストーリーを持つ企業は、競合がその構成要素(ベストプラクティス)だけを模倣すればするほど、相手の組織や戦略の整合性が崩れ、かえってパフォーマンスが低下することを知っている。だからこそ、トヨタ自動車などの優れた戦略を持つ企業は、自社の戦略を比較的オープンにする。秘密を明かしても、ストーリーを理解しない模倣は脅威にならないばかりか、相手の自滅を誘発するからだ。
「優れた戦略を一生懸命模倣しようとする行為自体が、競合他社のパフォーマンスを落とす。これこそが究極の競争優位だと思います」
変化の激しい現代でも、競争の本質は変わらない。しかし、その中で持続的な違いを生み出すのは、飛び道具のような華々しい打ち手ではない。一見地味で、時には非合理にさえ見える打ち手を、強力な因果の論理で紡ぎ上げた“痺れる”戦略ストーリーなのである。その構築こそが、次世代のリーダーに求められる核心的な能力だと、講演は締めくくられた。
※「異常が発生したら機械が直ちに停止して、不良品をつくらない」という考え方と、各工程で必要なものだけを、流れるように停滞なく生産する考え方(ジャスト・イン・タイム)により、高品質な製品を効率的に生産する目指した生産方式。
参考:トヨタ生産方式